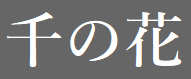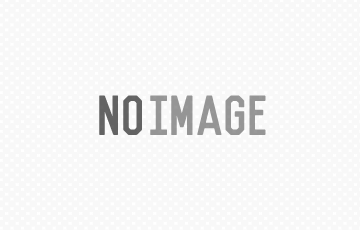本当はやりたくないのにやめられない
やりたいこと、好きなことをやったらいいという話をすると、何がやりたいのか、何が好きなのかわからないという人は結構います。
しかし、そのような方たちも、あれはやりたくない、これは嫌いだからやめたいということはわかっていることが多いです。
心の奥では「やめたい」「やりたくない」と思っているのに、やめられない苦しみ。
なぜやりたくないことを続けているのでしょうか?
やめることによるデメリットの方が大きいと無意識に思っているからですね。
確かに、何かを断るとか、やめる決断を相手に伝えるのは、勇気のいることですし、一時のストレスを強く感じるでしょう。
やめてみた後で得るメリットの方が大きいかもしれないのに、やめたら大変なことになる、と思うからやめられない。
特に仕事や結婚生活など、本当はもう終わりにしたいと思っていてもなかなか勇気がでないものです。
多くの場合、現状維持を続けるためだったり、これ以上悪化しないようにするためという理由です。
他人の目を気にし、他人の期待や要求に応えるために、本心を犠牲にしています。
例えば、親の期待に応えて一生懸命勉強し、大学に入ったけど、学んでいる内容に全く興味がわかない、ということもありますよね。
お金を出してもらっている立場なら、やめたくてもやめにくいですよね。
大学の場合は4年間なので、期限がわかっている分ちょっとは気楽かもしれません。
もしかしたら、途中で認識が変わって授業が面白いと感じるようになるかもしれませんし。
そうはいっても、親の機嫌を取るためにやりたくもないことをやっている時間はしんどいです。
親の方は「子どもがちゃんと自立して生きていけるように」という願いを抱いているわけですが・・・。
それが純粋なものではなく、子どもの将来が不安で、好きにさせたら将来どうなるかわからないから、その不安を解消させるために
子どもを自分の理想に当てはめている場合、子どもは息苦しくなってしまいます。
子どものことを信頼し、見守っているわけではなく、それは「監視」であり、「親自身の不安の解消」だからです。
他にも例を挙げると不安を解消するために恋人の行く先をいちいちチェックするという行動も同じですね。
数時間毎にしたくもない連絡をさせられたり。
恋人に連絡したくてするんじゃなくて、連絡しないと相手が不安になるから、やっているという状況です。
他には介護あるあるです。スピリチュアルケアをやっていると介護関係者の知り合いも多くなります。
よく耳にするのは、介護が必要な方の家族さんが、介護サービスに対して自分の理想や要求を押し付けてくるというもの。
特に一生懸命介護をしている家族さんが、他の人のやり方ではダメだと文句を言ってきたり、サービスの枠を越えた細かなことも要求してきたり。
他の家族のメンバーにも同じように自分と同レベルの世話を要求するのでうまくいっていない場合が多い。
下部に関連ページのリンクを張りましたが、自分でこの方法をやって潜在意識を整え、自然とやめられる方向へ持っていきました。
自分がやらなくてもいい、やりたくないことに時間を費やしていたら、あっという間に死を迎えます。
誰かの不安を解消するための行為、それはたいてい負担感がつきまといますね。期限がわからないものであればなおさら。
同じ「耐える」ことでも、自分を生かさない「我慢」ではなく、生かすため・開花のための「忍耐」を選びたいです。
小さなことからやめていく
いきなり「仕事を辞める」「離婚をする」など大きなことはハードルが高いですね。
やめるハードルが高いものではなく、小さなことからやめていく「実績」を作っていくことで、
次は中くらいのもの、次も中くらいのもの、次は中くらいよりややハードルが高いもの、と徐々にステップアップしていくでしょう。
今日もお読みくださりありがとうございました。
「やめる」と決断しても周囲が許してくれないだろうな、という場合。
周りに直接働きかけるのはかえって逆効果になったりしますよね。
先に自分の潜在意識を整え、「やめた状態」に先に自分がなってしまうのです。
未来の自分を先取りし、あとはセルフケアをするなり、好きなことをするなり、自分の内面を整えていく。
すると周りの状況も整い、やめられる状況が作られます。